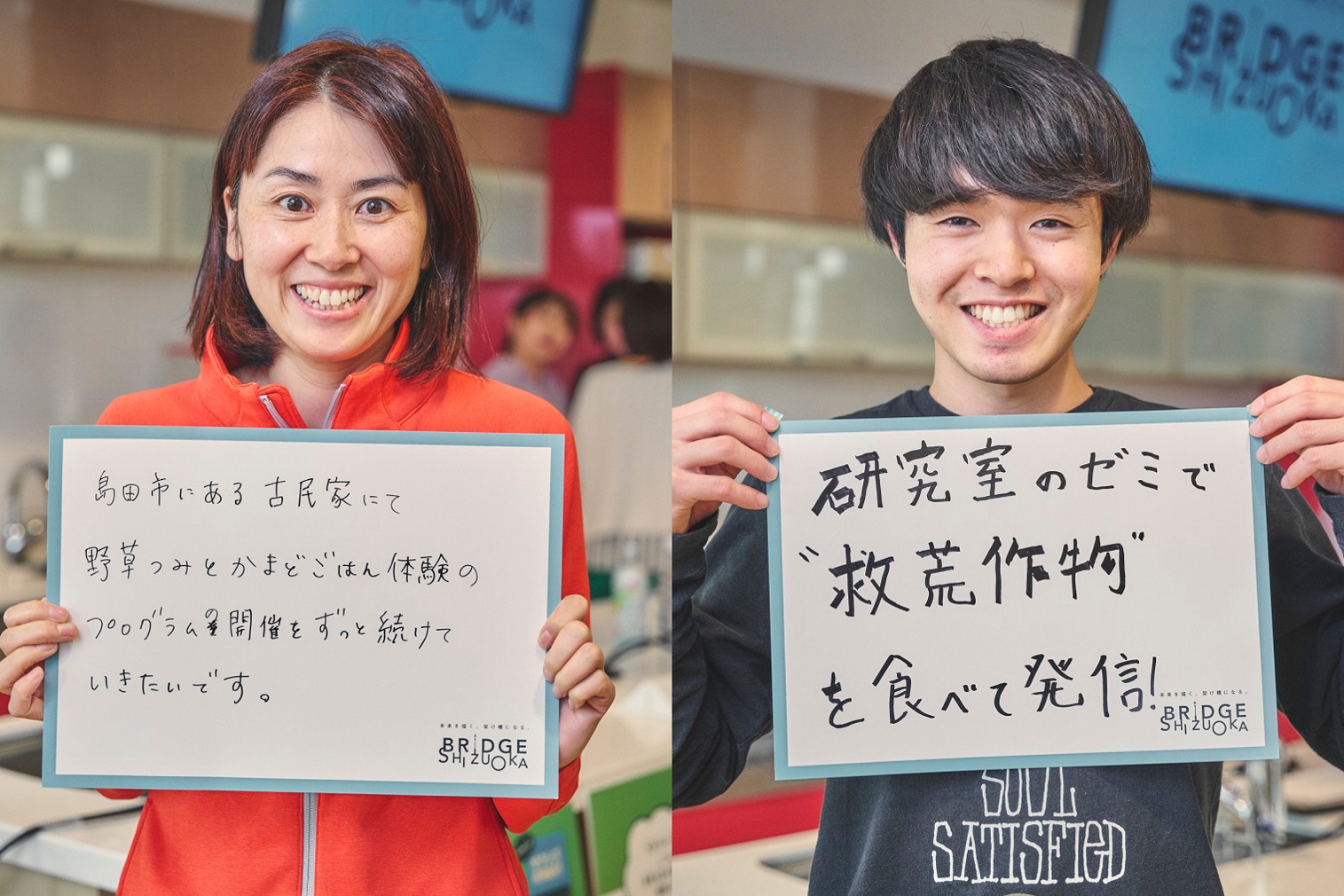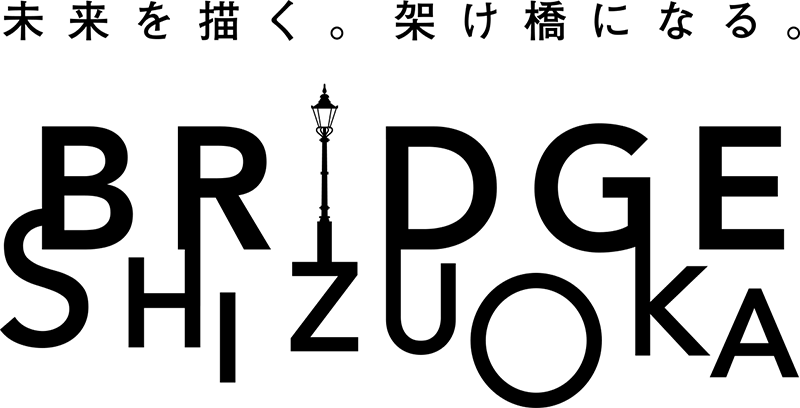テーマ 在来作物の魅力に触れる
静岡のみならず世界の在来作物と出会ってきたゲストとともに、実際に味わいながら、その魅力と可能性に触れてみる。


「弱者の戦略(新潮社)」「生き物の死にざま(草思社)」など著書は150冊以上。入試に使われる著者ランキング1位でも知られる。 2012年より静岡県の在来作物を調査・研究し、「しずおかの在来作物—風土が培うタネの物語(静岡新聞社)」をまとめている。54歳。
Moderator